「へぇ、後輩君と仲良くなれたかぁ」
その夜、また昨日と同じ店に由美を呼び出したおれは、今日あったことを話していた。
「由美の言ってくれたことがふっと頭に浮かんでさ。ああ、こういうことだったのかって思ったよ。やっぱ由美はすげぇな」
「でしょ。人事のエリートすごいんだから」
由美は心底 得意げな表情を見せる。
「今日はおごるわ」
「ええ~!嬉しい!ありがとう!って、どっちにしろ裕一の番だったでしょ!」
「…由美ってさ、たまの ノリが関西になるよな」
「あー、まぁね。これも人付き合いをうまくする方法の一つね。新人のときに、頑張って身につけたよ」
おとなしい性格の由美も、頑張って色々と人付き合いのテクニックを磨いたようだ。人事といえど、そこは営業に通じるものがあるらしい。
「そしたら次は、支店長の攻略だね!」
「支店長?そんな話になったっけか?」
「今後、黒岩板金の柏木って人に会いたいんでしょ?さらには向こうのミスを認めさせるために行くなら、今日と同じ裕一と後輩君が行っても追い払われるのがオチよ。こういうのは変化が大事なの。この場合の変化とは?」
「あー。さらに上を連れて行け、か」
「ご名答」
由美はニヤリと笑った。さらに上とは、言うまでもなく伊澤支店長のことだ。
「しかしあのへそ曲がりがついて来てくれるとは思えねぇよ。どうせ椅子にふんぞり返って、お前が責任持て~しか言わないぜ」
「裕一は嫌われてるんだねぇ」
「そりゃそうだ」
「なら、裕一から好きになっちゃえば?」
おれは飲んでいたビールを吐き出しそうになった。今日の由美はキラーパスが多い。
「そういう趣味はねんだけど」
「そういうことじゃなくて。信頼関係を作ろうって話をしてるの」
「あいつと、信頼ぃ?」
伊澤支店長のうざったい顔が思い浮かぶ。奴と信頼し合っている自分の姿なんか、想像もできない。
「裕一は嫌でも、こんな状況を打開するなら、支店長の肩書きを借りるしかないでしょう?そのためには、支店長と仲良くなるしかないじゃない」
「いや、由美の言いたいことは分かるけどさ…」
「裕一、上司は扱われる人じゃないの。こっちが操るものなの」
「上司を…操る…?」
考えたこともないことだ。
「人って単純でね、自分がおだてられたり、頼ってくれたり、感謝されたりすれば、悪い気は起きにくいものなの。裕一は、支店長さんに対してそういうことしてこなかったんじゃない?」
「そりゃそうだろ。足引っ張ったり、訳分からねぇ指示出すしかしねぇしさ」
「なら意識的に、支店長に相談したり、感謝したりしてみなよ。悪い気はしなくなるはずだよ。それから、今回の件の協力をお願いするの」
「…はぁ…」
あまりにも現実離れしたような話なので、おれは受け止めきれない。
「まぁ、騙されたと思ってやってみなよ。上司が自分の希望通りに動いてくれるようになると、気分いいよ」
由美はそう言うと爽やかに笑う。なかなかにブラックなことを言いながら、よくこんな明るい笑顔になれるものだ。どうも由美と比べてると 自分は子供のように思えてしまう。おれはまだ表情を取り繕ったり、演技をするのが 自分でも分かるほど下手なのだ。
しかし同時に、何とも言えない感情が高ぶってくるのを感じていた。おれが、伊澤支店長を操る、か。そういえば…
「由美、わりぃ、今からちと会社戻るわ」
「お、何か思いついたんだね。わかった。がんばってね!」
おれは鞄を掴むと、勢いよく席を立った。
おれは誰もいない真っ暗な事務所に戻ると、PCを立ち上げて企画書を作り始めた。
昨日伊澤支店長が言っていた、まとめ買いしてくれる客先には割り引きますという企画だ。
前述したように、このご時勢でまとめ買いを促すのはあまりにも愚かな行為。そのうち伊澤支店長は、そんな指示を出したことすら忘れるだろうから、完全にスルーをしようと思っていたのだ。
しかし、由美の話を聞いてこの考えが変わった。こんなクソのような企画でも、客先に話を通して少しでも売り上げアップになり、おれが「伊澤支店長のおかげです!」と目を輝かせて感謝したら、伊澤支店長はどう感じるだろう。おれに対する認識を、少しでも好転させてくれるかもしれない。そこで支店長の気が緩んだ一瞬の隙に、黒岩板金の同行を頼み込むのだ。
そのためには、今日の黒岩社長の対応を支店長に報告する前に、支店長の企画で実績を上げておく必要がある。チャンスは、せいぜい明日の午前中までだろう。この企画書を作成したら、明日は早めに家を出て、この企画を飲んでくれそうな客先に直行しなければならない。
誰もいない室内で、おれのキーボードを叩く音だけが響き渡る。時計の針は、11時を指していた。終電までに間に合うだろうか。今頃さっき飲んだ酒が回り始め、眠気が襲ってきている。
おれは栄養ドリンク を買いに行くべく、席を立った。
翌朝。眠気との格闘を しながら、おれはある客先へ直行した。
上場している大企業で、おれが新人の頃から担当している顧客だが、その担当者が今年の初めに変わった。挨拶に行って驚いたのだが、その新しい担当者は、大学時代所属していた登山サークルの後輩だったのだ。
3年間苦楽をともにした後輩が、大手の取引先の担当者になったのは、おれにとって本当に幸いだった。多少なら無理なお願いもしやすいからだ。
今回の支店長発案のクソ企画の犠牲には、この会社になってもらうことにしていた。
「在庫には困ってないんですけどねぇ…」
案の定、面会した後輩も契約書を見ながら渋い顔をする。契約書には、よく発注がかかる、在庫にしておいても損はないであろう種類のパイプが数十本、30万程度の金額が記載されている。
「ぶっちゃけ、こっちの社内で色々あってさ。一回発注かけて、後でキャンセルしてくれてもいいから」
こんな無理を話せるのは、多くの取引先の中でもここだけだろう。彼は困ったような顔をしながらも、それなら明日キャンセルの連絡を入れますから、と言いながらも契約書にサインをしてくれた。持つべきものは人脈だ。
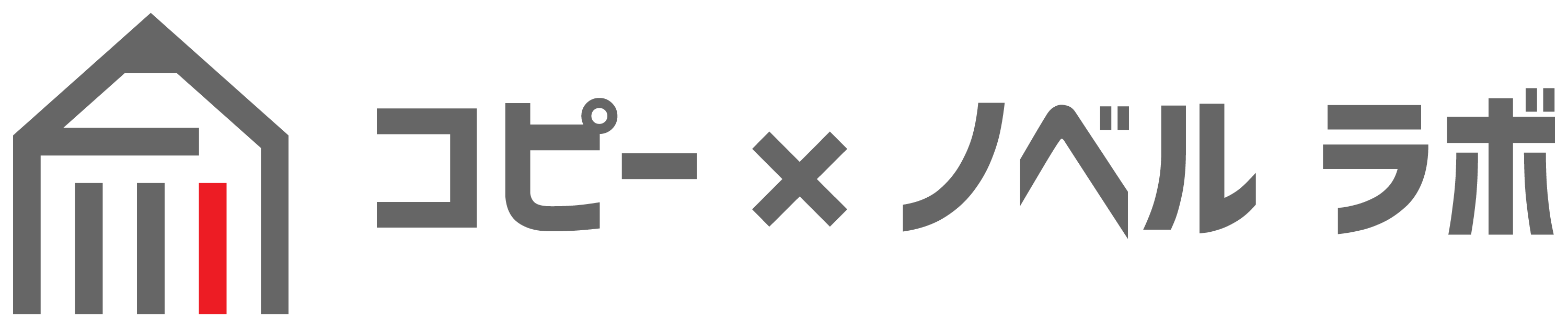


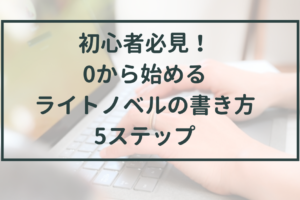






コメントを残す