「これが社畜ってもんだぜ。ったく、何が楽しいんだか」
おれは一気にビールを飲み干す。
「今日は大変だったんだね。お疲れ様」
隣の由美が、すかさず瓶ビールをついでくれた。今日のたまった鬱憤は、由美の笑顔を拝することで、何とか割り切れるようになってきている。
由美は、中学の同級生だ。2年のときに一度隣の席になったことはあったがそれほど仲良くはなかった。SNSを通じて再会したのは半年ほど前。お互いの勤めている会社が近かったことから仕事の後の飲み友達になり、お互い仕事の愚痴や趣味の話など、何でも語り合った。
それから由美が恋愛対象に変わるのにそう時間はかからなかった。
由美は、中学時代はおとなしく、クラスでも目立たない女友達とよくつるんでいた。しかし大人になってから再会した彼女は驚くほどきれいになり、上品な声で屈託ない笑い方が印象に残った。おとなしい性格には変わりないが、人の気持ちを察することがうまく、よくおれの考えていることを正確に当てた。それが、おれの心の中にスッとさりげなく入ってきてくれるようで心地よく、嬉しくもあり、再会して1週間も経たないうちにおれはもう惚れていた。
「それで月曜から呼び出して、私相手に飲んだくれてるわけだ」
「まったく、美人の顔でも拝ませてもらわなきゃやってらんねって」
「うまいね~」
「美人って由美のことじゃないけどな。そこの若い店員さんの…ぐえっ」
由美はおれの足をハイヒールのかかとでガッとつつく。しかしいたずらっぽく笑うその笑顔がかわいい。
会社の近くの狭くてお世辞にも清潔とはいえない居酒屋でも、由美がいてくれたら癒しの空間に早変わりするものだ。
「なぁ、由美の部署の上司はどんな感じ?おれのところほどうざくはねぇの?」
おれはぐったりテーブルに突っ伏した。
「私のところ?」
そういえば、お互い何でも気さくに話しているように感じていながら、由美の愚痴はあまり聞いていなかった気もする。由美はいわゆる聞き上手なのだ。
「めんどくさい上司はいっぱいいるけどね…でも結局みんな人だから」
「人?」
聞きなれない言葉に、思わず体を持ち上げる。
「上司でも部下でも同僚でも客先でも、結局はみんな人だから。好き嫌いとか、長所短所があるのは当然だと思ってるの。それで、その人のどこを見ればうまく付き合えるか考えてみると、以外に誰とでもうまくやっていけるよ」
「誰とでも…?んなまさかぁ」
「あー、疑ってる!人事部ホープの私が言うことなんだからね!」
由美は、大企業の人事部に所属している。面接や人事異動などを担当する仕事ということもあり、人を見る目はおれ以上に鋭いことは間違いない。
「んじゃあさ、もし由美がうちの会社にいたら、おれの上司とうまくやれると思う?」
「んー、そうだねぇ。3ヶ月くらいあれば」
「マジ?」
「うん。上司さんの好きなこととか、長所を見つけて、それを見ながら接していくんだよ」
「やつの長所…?そんなもの地球上に存在するのか?」
「おおげさな」
「そんなもんあったらレアメタルより貴重だぞ」
由美は声を上げて笑った。
「それにねー。人事から見たら、社畜ってのも、なかなか悪くないもんだよ?」
「社畜が、悪くない?」
「そ。数字ばっかり見てたら全然気付かないだろうけど。たまには視野を広げてみるのもいいかもよ」
数字ばかり見ている。それはおそらく営業の全社員がそうだろう。入社してから皆、上司、同僚、部下、全てが互いに追いつけ、追い越せの関係で、それはこれからも変わることはないだろう。
「言ってることがよく分からんなぁ…」
「あはは。そうかもね」
由美は言いながら、伝票を掴んで席を立ち上がった。
「帰るのか?」
「明日も早いからねぇ。また今度ゆっくり飲もう」
由美は前を向いたまま、おれに手でおいでおいでしながらレジへと向かう。飲み代は交互に払うのが暗黙の了解になっていた。前回はおれが払ったので、今回は由美が持つ番なのだ。もっとも前回は、なかなか良い値段のバーで飲んだのだが。
おれは何となくモヤモヤしたまま、由美の後を追う。今日は残念ながら、このまま帰る流れになりそうだ。
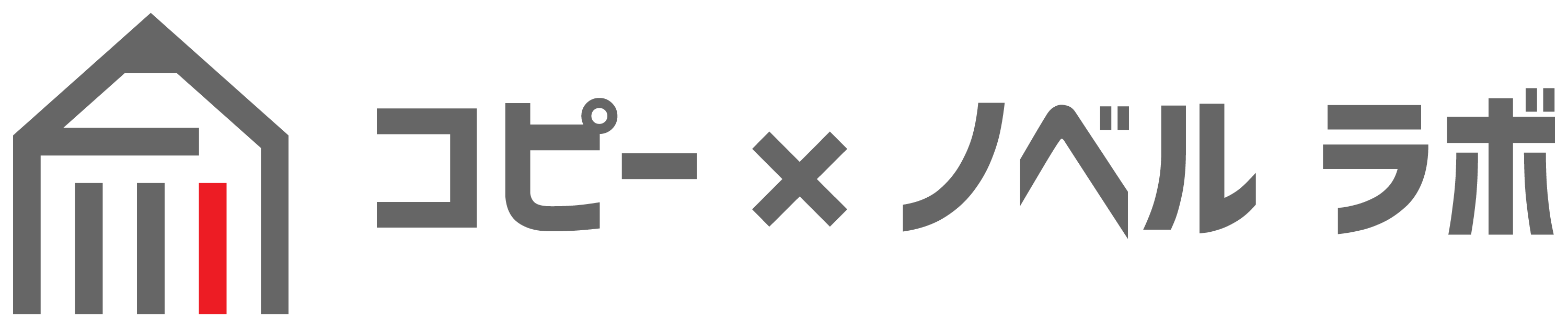



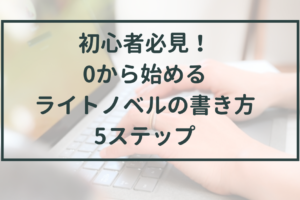






コメントを残す