「びええええ!!」
また小さな女の子に泣かれた。3歳くらいだろうか。
朝のさわやかな雰囲気の通学路には似つかわしくなく、けたたましい声を上げ泣き叫んでいる。
ただ、女の子が落としたハンカチを拾って渡しただけなのだが。
おれが「はい」、と目の前にハンカチを差し出し、女の子と目を合わせただけ。
だが女の子は一瞬にして口をへの字に曲げ、涙を溢れさせたかと思うと、この大音量だ。
原因はおれの人相の冷たさ。
繰り返すが、おれは小学校時代から「冷たい」とよく言われていた。
子供の時代から、お世辞にも明るい性格とは言えず、ついたあだ名は「ガリガリ君」。
痩せていたこともあるが、それ以上に「ガリガリ君アイスのような冷たさ」という意味だろう。
いつもおとなしく、表情が変化しないことに加え、無駄に目つきだけは鋭い。まるでゴル〇13のようだ。
普通に相手を見ているだけでも、怯えられることがよくあった。
というわけで、子供に泣かれることは悲しいかな慣れている。
女の子がハンカチを手に持っていることを確認すると、おれは学校に向かって歩き始めた。
学校へ着くと、いつものように誰と挨拶を交わすでもなく、黙々と靴を履き替えて教室へ向かう。
高校生には泣かれはしないが、いずれにしてもおれは不人気だ。
入学して半年近く経っても、友達も少なく(というかゼロ)、クラスではいつも一人だった。
こんなおれに近づいてくる人間もいるが、友好を求める人種ではない。
「おりゃ!アイスブレーイク!」
いつものように、ガラガラ声とともに攻撃を仕掛けてくるのは、同じクラスの荒谷勝治。
どこのクラスにも一人はいる、いわゆる「いじめっ子」だ。
何も部活はしてないくせに体格はいいから、ガリガリなおれに抵抗する術はない。
いつもされるがままに吹っ飛ばされたりしている。
今朝の荒谷は、おれが教室に向かって廊下を歩いていると、前から3人の男友達としゃべりながら歩いてきた。
すれ違いざまに、肩を思い切りぶつけてくる。
おれは廊下の窓ガラスに叩きつけられ、派手な音を立てて転んだ。
その音に、近くわ歩いていた何人かが振り向くが、我関せずとすぐに顔をそむける。
おれはさすがにイラッとして、荒谷を睨んだ。
「おー、こえこえ、その目つき。夏にはちょうどいい涼しさだなオイ」
大げさに肩をすくめながら荒谷は去っていく。
「おい、宮門にあんま絡み過ぎない方がいいんじゃね?あいつナイフとか普通に持ってそうだよ」
「んなわけねぇだろ?持ってたってなんもできねぇよ」
他の男子が荒谷を諌めていたようだが、彼は無論言うことを聞かない。
諌める、というより、その男子は本気でおれの報復を怖がっていたようだ。
おれがそんなことするはずもなかろうに…
そんな誤解を生んでしまうのが、おれ自身の雰囲気。誰からも必要とされず、マイナスの効果のみを周囲に及ぼす。
ため息をついて壁から離れて立ち上がり、歩き出そうした次の瞬間。
「うお…」
おれはギョッとして足を止めた。
「何?今のリアクション。それって驚いたの?」
おれの目の前には、同じクラスの福田絵美が立ちはだかっていた。
うん、立ちはだかるという表現が一番しっくりくる。
まるで、おれの進行方向を妨げるかの如く、おれの目と鼻の先に立っているのだ。
「うーん、驚いているんだろうけど…ほーんと宮門君て、顔変わらないよねぇ…むしろ少し冷めてるような」
福田はおれの顔をじろじろ覗き込む。
彼女はいわゆる「カワイイ系」の女子。
どのクラスでも、なんとなくカースト制のように一人一人に序列がついているが、彼女は間違いなく上位に食い込む存在だ。
よく笑う明るい性格で、休み時間の教室は、どこにいても彼女の笑い声が聞こえた。
自然友達も多く、いつも周りには福田を囲う取り巻きが、男女問わずにいた。
ショートカットがよく似合い、振り向くと柔らかそうに揺れる髪に、男なら誰でも一瞬目を奪われるだろう。
生徒会書記、演劇部部長といった肩書も、彼女の魅力にプラスされている。
「おれに何か用?」
荒谷にちょっかいを出された後だ。彼女もおれをからかいに来たのかと不審に感じた。
友達もいないおれと福田の接点は、当然のように一切なく、言葉を交わしたことも数えるほどだろう。
おれにここまでの興味を示す彼女が、不気味に見えた。
「ね、いきなり提案なんだけどさ、私とお笑いやってみない?」
「…………………………は?」
こんな長い間をとったことがないほど、おれはしばらく絶句した。
「だからさぁ、お笑いだよ。漫才とか見たことない?テレビとかで」
「そりゃあ、あるけど…」
「それをやろうって言ってるの!私と」
「……………は?」
再び聞き返しても、全く彼女の真意が見えない。本気で言っているんだろうか。
「知ってる?お笑いって、ギャップがあればあるほど面白いんだよ。ハイテンションの私と、ローテンションの宮門君が組むと、そのギャップがガッツリ生きて、面白い漫才ができると思うんだよねぇ」
「……………はぁ」
「私、小学校の高学年くらいからお笑いにはまっててね、いつか自分でもやりたいと思ってるんだぁ。演劇部入ったのも、発声練習とかがお笑いに生かせると思ったからで」
「……………はぁ」
「もうすぐ文化祭があるじゃん?体育館で誰でも出場できるテーマフリーの発表会があるから、そこにエントリーしたいの!」
「……………はぁ」
「だから、組もう!」
福田の発する言葉の一つ一つに、おれはいちいち口をあんぐり開けるしかできない。
彼女の言っていること全てが、突拍子もなく訳が分からない。
しかし、無邪気にお笑いについて話す彼女は、冗談を言っているようには見えないのも事実だ。
「………えっと、まずさ、本気?」
「へ?これだけ迫って、ウソに見える?」
「いや、おれにそんなこと言う人がいるとは思えなかったからさ」
「あー。まぁ言ってることは普通じゃないことは分かってるよ。でも、回りくどく言っても仕方ないからねぇ。単刀直入に私の想いをぶつけてみた」
福田は腕を組んで、自慢げにふん!と鼻を鳴らす。
「でも、悪い。おれにお笑いなんて無理だよ。そういうので笑ったことないし、まして人を笑わせるなんて…」
「へ?宮門君が笑う必要ないよ?周りが笑ってくれれば、自然に自分も笑えるもんだよ」
「…は?」
福田は心底不思議そうな顔をするが、不思議なのはおれの方だ。
「まぁ、いきなり決めてなんて言わないよ。でも考えておいて。じゃね!遅れないようにね」
福田はそれだけ言うと踵を返し、短い髪を揺らしながら教室に走っていく。
おれはしばらくその後ろ姿を茫然と眺めていた。
おれが…お笑い…?人から冷たいとばかり言われるおれが、人を笑わすことなんて…
おれは、今起きたことが受け入れられないまま、ふらふらと教室へ向かった。
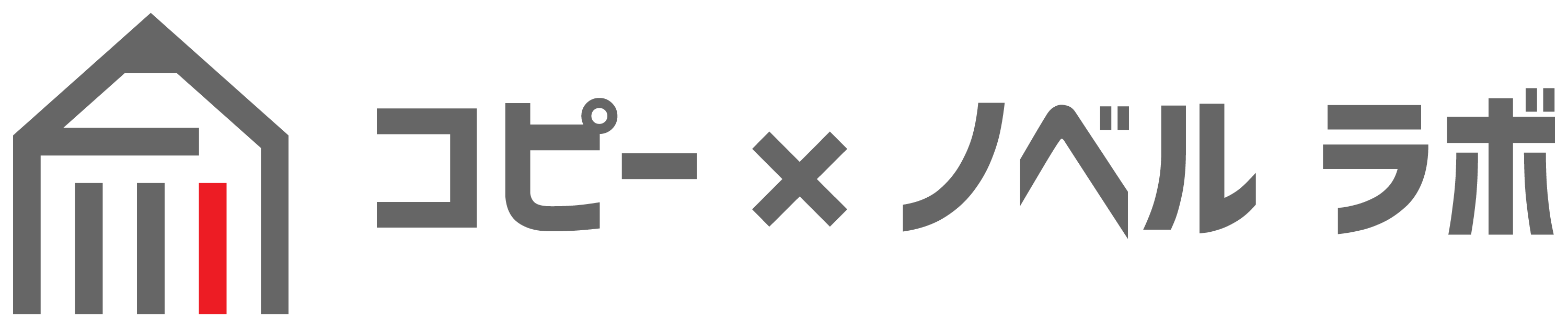





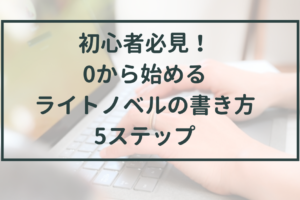





コメントを残す